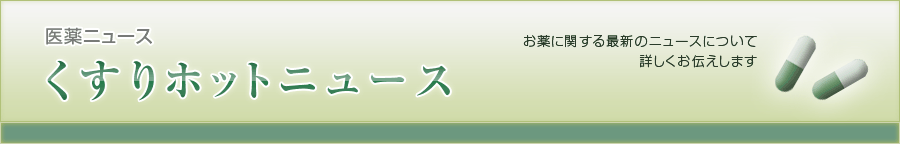厚生労働省は、6月30日、令和2年(2020)患者調査(確定数)の結果を公表しました。
患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況などを調査し、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。調査は3年ごとに実施しており、今回は、全国の医療施設のうち、病院6,284施設、一般診療所5,868施設、歯科診療所1,277施設を抽出し、これらの施設を利用した入院・外来患者約211万人、退院患者約104万人が対象となりました。入院・外来患者は令和2年10月の医療施設ごとに指定した1日、退院患者は令和2年9月の1か月間を調査期間としました。
令和2年調査については、新形コロナウイルス感染症の影響下であること、総患者数については推計方法の見直しを、退院患者の平均在院日数及び在院期間については算出に必要な入院年月日に所要の対応を行っています。
【調査結果のポイント】
◇推計患者数
調査日に全国の医療施設で受療した推計患者数は、「入院」1,211.3千人、「外来」7,137.5千人である。
(1) 施設の種類・性・年齢顔級別
「入院」1,211.3千人について、施設の種類別にみると、「病院」1,177.7千人、「一般診療所」33.6千人、性別にみると、「男」558.6千人、「女」652.8千人、年齢階級別にみると、「65歳以上」904.9千人、「70歳以上」805.5千人、「75歳以上」663.6千人となっている。
「外来」7,137.5千人について、施設の種類別にみると、「病院」1,472.5千人、「一般診療所」4,332.8千人、「歯科診療所」1,332.1千人、性別にみると、「男」3,050.0千人、「女」4,087.5千人、年齢階級別にみると、「65歳以上」3,616.8千人、「70歳以上」2,963.9千人、「75歳以上」2,077.3千人となっている。
推計患者数の年次推移をみると、入院では平成20年から減少しており、外来では平成23年からほぼ横ばいとなっている。
年齢顔級別にみると、入院ではいずれの年齢でも平成29年に比べ減少しており、外来では平成23年以降ほぼ横ばいとなっている。
(2) 傷病分類別
推計入院患者数を傷病分類別にみると、多い順に「精神及び行動の障害」236.6千人、「循環器系の疾患」198.2千人、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」134.5千人となっている。
推計外来患者数では、多い順に「消化器系の疾患」1,270.8千人、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保険サービスの利用」1,001.3千人、「筋骨格系及び結合組織の疾患」906.0千となっている。
(3) 在宅患者の状況
調査日に在宅医療を受けた推計外来患者数は173.6千人であり、これを施設の種類別にみると、「病院」22.3千人、「一般診療所」110.3千人、「歯科診療所」40.9千人となっている。
在宅医療の種類別にみると、総数では「往診」52.7千人、「訪問診療」105.7千人、「医師・歯科医師以外の訪問」15.2千人となっている。
年次推移をみると、在宅医療を受けた推計患者数は、平成20年からは増加しているが、令和2年では減少している。
(4) 入院(重症度等)の状況
入院(重症度等)の状況をみると、「生命の危険がある」5.6%、「生命の危険は少ないが入院治療を要する」76.7%、「受け入れ条件が整えば退院可能」11.6%、「検査入院」0.9%となっている。
◇受療率
全国の受療率(人口10万対)は、入院960、外来5,658である。
(1)性・年齢顔級別
性別にみると、入院では「男」910、「女」1,007、外来では「男」4,971、「女」6,308となっており、年齢階級別にみると、入院では「65歳以上」2,512、「70歳以上」2,899、「75歳以上」3,658、外来では「65歳以上」10,045、「70歳以上」10,665、「75歳以上」11,167となっている。
(2)傷病分類別
傷病分類別にみると、入院では、高い順に「精神及び行動の障害」188、「循環器系の疾患」157、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」107となっている。外来では、「消化器系の疾患」1,007、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保険サービスの利用」794、「筋骨格系及び結合組織の疾患」718となっている。
(3)都道府県別
都道府県(患者住所地)別にみると、入院では「高知」が1,897と最も高く、次いで「鹿児島」1,810、「長崎」1,679となっている。また「神奈川」が654と最も低く、次いで「東京」669、「愛知」695となっている。
外来では、「香川」が6,729と最も高く、次いで「佐賀」6,599、「山形」6,353となっている。また、「沖縄」が4,393と最も低く、次いで「石川」4,656、「千葉」4,829となっている。
◇退院患者の平均在院日数
(1)施設の種類・年齢顔級別
令和2年9月中の全国の退院患者について、在院日数の平均である平均在院日数を施設の種類別にみると、「病院」33.3日、「一般診療所」19.0日となっている。
年齢階級別にみると、「65歳以上」が最も長くなっている。
(2)傷病分類別
退院患者の平均在院日数を傷病分類別にみると、長い順に「精神及び行動の障害」294.2日、「神経系の疾患」83.5日、「循環器系の疾患」41.5日となっている。
(3)推計退院患者数の構成割合
退院患者の在院期間別に推計退院患者数の構成割合をみると、病院は「0~14日」が66.8%、「15~30日」16.2%、一般診療所は「0~14日」が81.4 %、「15~30日」が8.5%となっている。
◇入院前の場所・退院後の行き先
入院前の場所についてみると、推計退院患者1,340.9千人のうち「家庭」が87.0%となっている。
また、退院後の行き先についてみると、「家庭」が82.4%となっている。
◇傷病分類別の総患者数
総患者数を傷病分類別でみると、多い順に「循環器系の疾患」20,411千人、「消化器系の疾患」17,619千人、「内分泌、栄養及び代謝疾患」11,479千人となっている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/20/index.html