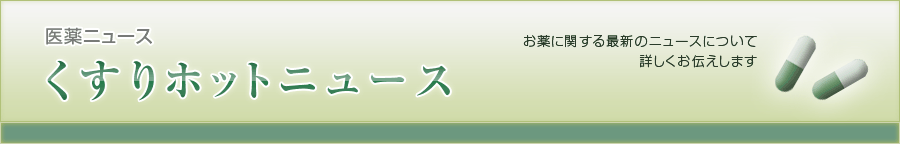厚生労働省は、11月30日、「令和2年度国民医療費」を公表しました。
国民医療費は、その年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の推計です。ここでいう費用とは、医療保険などによる給付のほか、公費負担、患者負担によって支払われた医療費を合算したものです。
国民医療費には、医科診療医療費、歯科診療医療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等は含みますが、保険診療の対象とならない費用や、正常な妊娠・分娩、健康診断、予防接種など、傷病の治療以外の費用は含みません。
1 国民医療費の状況
令和2年度の国民医療費は42兆9,665億円、前年度の44兆3,895億円に比べ1兆4,230億円、3.2%の減少となっている。
人口一人当たりの国民医療費は34万600円、前年度の35万1,800円に比べ1万1,200円、3.2%の減少となっている。
2 制度区分別国民医療費
制度区分別にみると、公費負担医療給付分は3兆1,222億円(構成割合7.3%)、医療保険等給付分は19兆3,653億円(同45.1%)、後期高齢者医療給付分は15兆2,868億円(同35.6%)、患者等負担分は5兆1,922億円(同12.1%)となっている。
対前年度増減率でみると、公費負担医療給付分は3.3%の減少、医療保険等給付分は3.4%の減少、後期高齢者医療給付分は2.4%の減少、患者等負担分は4.8%の減少となっている。
3 財源別国民医療費
財源別にみると、公費は16兆4,991億円(構成割合38.4%)、そのうち国庫は11兆245億円(同25.7%)、地方は5兆4,746億円(同12.7%)となっている。保険料は21兆2,641億円(同49.5%)、そのうち事業主は9兆1,483億円(同21.3%)、被保険者は12兆1,159億円(同28.2%)となっている。また、その他は5兆2,033億円(同12.1%)、そのうち患者負担は4兆9,516億円(同11.5%)となっている。
4 診療種類別国民医療費
診療種類別にみると、医科診療医療費は30兆7,813億円(構成割合71.6%)、そのうち入院医療費は16兆3,353億円(同38.0%)、入院外医療費は14兆4,460億円(同33.6%)となっている。また、歯科診療医療費は3兆22億円(同7.0%)、薬局調剤医療費は7兆6,480億円(同17.8%)、入院時食事・生活医療費は7,494億円(同1.7%)、訪問看護医療費は3,254億円(同0.8%)、療養費等は4,602億円(同1.1%)となっている。
対前年度増減率をみると、医科診療医療費は3.7%の減少、歯科診療医療費は0.4%の減少、薬局調剤医療費は2.5%の減少となっている。
5 年齢階級別国民医療費
年齢階級別にみると、0~14歳は2兆1,056億円(構成割合4.9%)、15~44歳は5兆129億円(同11.7%)、45~64歳は9兆4,165億円(同21.9%)、65歳以上は26兆4,315億円(同61.5%)となっている。
人口一人当たり国民医療費をみると、65歳未満は18万3,500円、65歳以上は73万3,700円となっている。そのうち医科診療医療費では、65歳未満が12万2,300円、65歳以上が54万8,400円となっている。歯科診療医療費では、65歳未満が2万200円、65歳以上が3万2,800円となっている。薬局調剤医療費では、65歳未満が3万5,300円、65歳以上が12万3,900円となっている。
また、年齢階級別国民医療費を性別にみると、0~14歳の男は1兆1,627億円(構成割合5.5%)、女は9,429億円(同4.3%)、15~44歳の男は2兆2,664億円(同10.8%)、女は2兆7,465億円(同12.5%)、45~64歳の男は5兆143億円(同23.9%)、女は4兆4,022億円(同20.0%)、65歳以上の男は12兆5,445億円(同59.8%)、女は13兆8,870億円(同63.2%)となっている。
人口一人当たり国民医療費をみると、65歳未満の男は18万4,700円、女は18万2,200円、65歳以上の男は80万2,200円、女は68万1,200円となっている。
6 傷病分類別医科診療医療費
医科診療医療費を主傷病による傷病分類別にみると、「循環器系の疾患」6兆21億円(構成割合19.5%)が最も多く、次いで「新生物<腫瘍>」4兆6,880億円(同15.2%)、「筋骨格系及び結合組織の疾患」2兆4,800億円(同8.1%)、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」2兆4,274億円(同7.9%)、「腎尿路生殖器系の疾患」2兆2,733億円(同7.4%)となっている。
年齢階級別にみると、65歳未満では「新生物<腫瘍>」1兆5,816億円(同14.3%)が最も多く、65歳以上では「循環器系の疾患」4兆7,908億円(同24.2%)が最も多くなっている。
また、性別にみると、男では「循環器系の疾患」(同21.0%)、「新生物<腫瘍>」(同16.7%)、「腎尿路生殖器系の疾患」(同8.4%)が多く、女では循環器系の疾患」(同18.1%)、「新生物<腫瘍>」(同13.8%)、「筋骨格系及び結合組織の疾患」(同10.2%)が多くなっている。
7 都道府県別国民医療費
都道府県(患者住所地)別にみると、東京都が4兆2,972億円と最も高く、次いで大阪府が3兆2,991億円、神奈川県が2兆7,925億円となっている。また、鳥取県が1,984億円と最も低く、次いで島根県が2,595億円、福井県が2,600億円となっている。
人口一人当たり国民医療費をみると、高知県が45万7,600円と最も高く、次いで鹿児島県が42万6,700円、長崎県が42万1,000円となっている。また、埼玉県が29万8,200円と最も低く、次いで千葉県が29万9,700円、神奈川県が30万2,300円となっている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin//hw/k-iryohi/20/dl/data.pdf