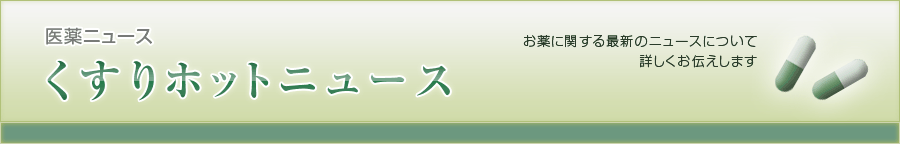鷹の爪団とコラボの動画「第二話業界団体の取り組み」を公開開始 日本ジェネリック製薬協会
日本ジェネリック製薬協会(GE薬協)は、10月6日から、鷹の爪団とコラボレーションした動画「スクープ!鷹の爪団 第二話業界団体の取り組み」の公開を開始しました。~ジェネリック医薬品業界で一体何が起きたのか?そして未来に何が起こるのか?鷹の爪団が導き出す真実とは?!目指せ大スクープ!~
鷹の爪団の取材を通じて、ジェネリック医薬品業界に生じている問題について分かりやすく紐解くと共に、過去の不祥事と真摯に向き合い、業界全体で信頼回復のために取り組むジェネリック医薬品業界の実情やその行く末について、鋭く迫る内容を展開します。
順次、第三話を公開する予定です。
特設サイト: https://www.jga.gr.jp/jga_scoop_takanotsume.html
配信先: Youtube DLEチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UCy4lGSE0rADMfp12aUxpBLw
動画本編#2 https://youtu.be/2yEBD26ImKY