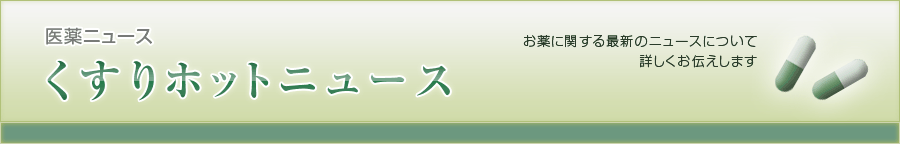厚生労働省は、3月22日、2月18日及び19日に実施した第108回薬剤師国家試験の合格発表を行いました。
全体では出願者数15,334名(このうち新卒者9,595名)、受験者数13,915名(このうち新卒者8,548名)、合格者数9,602名(このうち新卒者7,254名)、合格率69.00%(このうち新卒者84.86%)となっています。
この結果を男女別、設置主体別にみると次の通りです。
男女別合格率①
出願者:総数15,334名、男6,047名(39.44%)、女9,287名(60.56%)
受験者:総数13,915名、男5,361名(38.53%)、女8,554名(61.47%)
合格者:総数9,602名、男3,549名(36.96%)、女6,053名(63.04%)
合格率:総数69.00%、男66.20%、女70.76%
男女別合格率②
6年制新卒=出願者:総数9,595名、男3,482名(36.29%)、女6,113名(63.71%)
受験者:総数8,548名、男3,025名(35.39%)、女5,523名(64.61%)
合格者:総数7,254名、男2,589名(35.69%)、女4,665名(64.31%)
合格率:総数84.86%、男85.59%、女84.46%
6年制既卒=出願者:総数5,474名、男2,401名(43.86%)、女2,944名(57.14%)
受験者:総数5,146名、男2,202名(42.79%)、女2,944名(57.21%)
合格者:総数2,267名、男915名(40.36%)、女1,352名(59.64%)
合格率:総数44.05%、男41.55%、女45.92%
その他= 出願者:総数265名、男164名(61.89%)、女101名(38.11%)
受験者:総数221名、男134名(60.63%)、女87名(39.37%)
合格者:総数81名、男545(55.56%)、女36名(44.44%)
合格率:総数36.65%、男33.58%、女41.38%
設置主体別合格率
6年制新卒=出願者:総数9,595名、国立474名、公立250名、私立8,871名
受験者:総数8,548名、国立471名、公立250名、私立7,827名
合格者:総数7,254名、国立426名、公立228名、私立6,600名
合格率:総数84.86%、国立90.45%、公立91.20%、私立84.32%
6年制既卒=出願者:総数5,474名、国立73名、公立44名、私立5,357名
受験者:総数5,146名、国立564、公立38名、私立5,044名
合格者:総数2,267名、国立34名、公立21名、私立2,212名
合格率:総数44.05%、国立53.13%、公立55.26%、私立43.85%
その他= 出願者:総数265名、国立84名、公立26名、私立124名
受験者:総数221名、国立73名、公立24名、私立124名
合格者:総数81名、国立42名、公立16名、私立23名
合格率:総数36.65%、国立57.53%、公立66.67%、私立18.55%
合計= 出願者:総数15,334名、国立631名、公立320名、私立14,383名
受験者:総数13,915名、国立608名、公立312名、私立12,995名
合格者:総数9,602名、国立502名、公立265名、私立8,835名
合格率:総数69.00%、国立82.57%、公立84.94%、私立67.99%
都道府県別合格者数(合格証書の都道府県別送付枚数)は、東京都1,129名、大阪府790名、神奈川県722名、埼玉県619名、千葉県597名、兵庫県493名、愛知県489名、福岡県394名、北海道353名、広島県291名の順です。
大学別合格率は、国公立では、①千葉大学91.30%(6年制卒業者の新卒94.87%、既卒80.00%、その他50.00%)、②東北大学89.66%(6年制卒業者の新卒100.00%、既卒50.00%、その他71.43%)、③静岡県立大学89.11%(6年制卒業者の新卒95.12%、既卒55.56%、その他70.00%)、④北海道大学87.50%(6年制卒業者の新卒93.10%、既卒100.00%、その他80.00%)、⑤名古屋市立大学86.84%(6年制卒業者の新卒94.64%、既卒58.82%、その他100.00%)の順。私学では①名城大学93.84%(6年制卒業者の新卒96.84%、既卒80.56%、その他0.00%)、②昭和大学91.15%(6年制卒業者の新卒95.18%、既卒68.00%、その他0.00%)、③医療創生大学88.52%(6年制卒業者の新卒91.23%、既卒50.00%、その他なし)、④京都薬科大学88.45%(6年制卒業者の新卒90.91%、既卒70.27%、その他33.33%)、⑤立命館大学87.30%(6年制卒業者の新卒98.98%、既卒46.43%、その他なし)、⑥近畿大学85.88%(6年制卒業者の新卒94.26%、既卒62.22%、その他90.00%)、⑦明治薬科大学85.67%(6年制卒業者の新卒92.63%、既卒59.72%、その他66.67%)、⑧北里大学85.12%(6年制卒業者の新卒87.04%、既卒74.36%、その他66.67%)、⑨星薬科大学85.00%(6年制卒業者の新卒90.56%、既卒66.15%、その他50.00%)、⑩慶應義塾大学84.24%(6年制卒業者の新卒89.58%、既卒55.56%、その他0.00%)となっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199343_00010.html