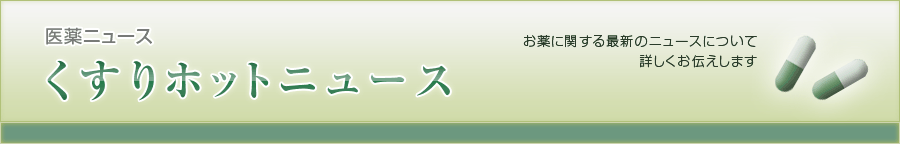令和5年度「保健師活動領域調査(領域調査)」の結果を公表 厚生労働省
厚生労働省は、9月29日、令和5年度「保健師活動領域調査(領域調査)」の結果を公表 しました。自治体に勤務する保健師の活動領域の実態を把握するため、自治体に所属する全ての保健師を対象とする令和5年度「保健師活動領域調査(領域調査)」を実施し、その結果を取りまとめて公表したものです。
【調査結果のポイント】
〇自治体別常勤保健師数
常勤保健師数の合計は、前年度より525人増加し38,528人となり、このうち都道府県の保健師は前年度より120人増加し5,795人(全国総数の15.0%)、市区町村の保健師は前年度より405人増加し32,733人(同85.0%)となっている。
〇所属部門別常勤保健師数
都道府県では、本庁に1,016人(都道府県総数の17.5%)、保健所に4,222人(同72.9%)が所属している。
市区町村では、本庁に11,650人(市区町村総数の35.6%)、保健所に4,186人(同12.8%)、市町村保健センターに11,640人(同35.6%)が所属している。
〇常勤保健師の退職者数・採用者数
退職者数は、都道府県では前年度より33人増加し369人(全退職者数の16.7%)、市区町村では前年度より31人増加し1,844人(同83.3%)となっている。
採用者数は、都道府県では前年度より63人増加し634人(全採用者数の21.2%)、市区町村では前年度より129人増加し2,360人(同78.8%)となっている。
〇統括保健師を配置している自治体数及び所属区分別統括保健師数
統括保健師は、都道府県では47自治体全てに、市区町村では1,149自治体(全市区町村の66.0%)において配置されている。
統括保健師の所属区分は、本庁が598人(全統括保健師の50.0%)、保健所が57人(同4.8%)、市町村保健センターが416人(同34.8%)、その他が125人(同10.5%)となっている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/katsudou/09/ryouikichousa_r05.html